2025.04.28

気候変動の影響によって、熱中症の発生リスクは季節を問わず高まっています。屋外で作業する建設現場や、機械熱がある環境の製造業だけでなく、オフィスや飲食店でも発生事例は増加傾向です。
企業には法的義務と社会的責任の両面から、従業員の健康と安全を守る対策が求められています。
この記事では、熱中症対策が企業に求められる背景や企業の義務、暑さ指数の目安と勤務体制・健康管理の工夫、業種別の具体策と成功事例を詳しく紹介します。
「【熱中症予防】現場で実践!安全を守る対策と応急処置の基本」の記事へ
職場における熱中症予防は、厚生労働省の第14次労働災害防止計画で目標が設定されています。
そのため、企業にとって、「職場における熱中症予防基本対策要綱」に基づき働く人々の健康を守ることは重要な義務となっています。
ここでは、職場での熱中症リスクが高まる理由や労働安全衛生法と企業の義務、熱中症による業務への影響について理解を深めていきましょう。
職場における熱中症リスクは、作業環境や健康状態が大きく影響しています。
作業環境として、炎天下の屋外作業に加え、炉や機械の輻射熱が蓄積する屋内作業場はリスクが高い環境です。
特に、湿度75%以上かつ気温30℃超などの高温・多湿環境では、汗が蒸発しにくくなり、脱水状態が引き起こされやすくなります。
ただし、真夏の日差しが強い時期だけではなく、梅雨から夏季になる暑くなり始めの時期も熱中症の発生リスクが高まるので、油断は禁物です。
特に、身体が暑さに慣れていない段階での重労働、連続した作業時間といった作業特性も、リスクが高まる要因です。作業服においても、通気性や吸湿性の悪い衣服や保護具を着用していると、汗をかいても体温が下がりにくく、熱中症が起きやすくなります。
さらに、従業員の健康状態も熱中症の発生に大きく影響する問題です。糖尿病や高血圧症、心疾患などの病気を抱えている場合は、脱水状態を引き起こしやすくなります。
自律神経に関連する薬を服用している人においても、発汗や体温調節機能が阻害されやすいでしょう。
他にも、風邪や感染症などで発熱している人、下痢で脱水状態になっている人、皮下脂肪が厚い人なども、熱中症のリスクが高いです。
このように、職場における熱中症は、屋内外や季節を問わずにリスクがあり、企業は常に予防と対策の実施が求められているのです。
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とした法律です。
熱中症対策においては、WBGT(暑さ指数)の測定や作業管理、健康診断結果に基づく対応などが義務付けられています。
実施項目の一例は、以下のとおりです。(義務規定、努力義務を含む)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| WBGT(暑さ指数)の活用 | ・作業場所にWBGT測定器を設置し、WBGT(暑さ指数)を計測する ・冷房により作業場所のWBGT(暑さ指数)の低減を図る ・基準値を超える場合は、熱中症予防対策を徹底する |
| 休憩場所の整備 | ・冷房を備えた場所や日陰の涼しい場所を設ける ・氷、冷たいおしぼり、シャワーなどの身体を適度に冷やせる設備を設ける |
| 熱への順化 | ・計画的に熱への順化期間を設ける |
| 水分及び塩分の摂取 | ・自覚症状の有無にかかわらず、水分や塩分の作業前後の摂取、作業中の定期的な摂取を指導・徹底する |
| 服装等 | ・吸湿性や通気性の良い服装を着用させる ・身体を冷却する服を着用させる |
| 健康管理 | ・健康診断結果に基づく対応を徹底する ・睡眠不足、体調不良、前日の飲酒、朝食の未摂取など留意の上、日常の健康管理を指導する ・作業開始前に労働者の健康状態を確認する ・休憩場所に体温計を備えておく |
| 救急処置 | ・熱中症の症状が現れた場合は、涼しい場所で身体を冷し、水分や塩分を摂取させる ・必要に応じ、救急隊を要請する |
詳細は、厚生労働省「職場における熱中症の予防について」を参照。
2025年6月施行の改正労働安全衛生規則では、「WBGT(暑さ指数)28以上または気温31℃以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超える作業」において、対策が義務付けられます。企業が対策を怠った場合は、罰則が科せられる可能性があります。
職場における熱中症は、労働災害のリスクを高めるだけでなく、労働生産性の低下や品質不良の増加といった業務効率の悪化にも繋がります。熱中症により、集中力や判断力の低下が生じることが要因の一つです。
ある研究では、暑熱ストレス下で作業する労働者の30%に生産性の低下を認めたという報告があります。また、別の報告では、気温が20℃を超えると生産性が低下し始め、WBGT(暑さ指数)が24を超えると1上がるごとに2.6%ずつ生産性が低下するとされています。
厚生労働省の「令和5年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」によると、2023年に職場で熱中症を発症した労働者は1,106 人に上り、うち31人が死亡しています。
特に建設業や製造業といった高温多湿な環境下で作業を行う業種では、熱中症のリスクが高く、適切な対策を講じることが急務となっています。
温暖化が進行する現状では、今後も熱中症のリスクは上昇すると予想されており、職場における熱中症対策はますます重要な労働安全衛生上の課題となりつつあります。
企業は、労働者の健康と安全を守るとともに、業務効率の維持・向上を図るためにも、積極的に熱中症対策に取り組む必要があるのです。
熱中症対策の指標として、WBGT(暑さ指数)が重要視されています。この数値を活用し、勤務体制や健康管理を最適化することで、職場の安全性が向上します。
ここでは、WBGT(暑さ指数)の活用方法や効果的なシフト管理、健康管理の手段について見ていきましょう。
熱中症対策の鍵は、暑さを客観的な数値で把握することです。そこで活用したいのがWBGT(暑さ指数)です。WBGT(暑さ指数)は、気温・湿度・輻射熱の3つの要素を総合的に評価する指標で、国際規格にも採用されています。
環境省の熱中症予防情報サイトでは、全国各地のWBGT(暑さ指数)をリアルタイムで公開しており、誰でも簡単にアクセスできるため、日々の業務管理に役立てられます。
また、WBGT(暑さ指数)は、体感温度に近い値を示すことも可能です。例えば、気温が同じ32℃でも、湿度が高い日や直射日光が強い日にはWBGT(暑さ指数)が高くなり、熱中症のリスクも高まります。WBGT(暑さ指数)の目安としては、28を超えると厳重警戒、31を超えると危険と判断し、作業環境に応じて適切な対策を講じることが重要です。
測定方法としては、専用のWBGT測定器を使用することが一般的です。WBGT測定器には、卓上型や携帯型、リストバンド型など様々な種類があるため、作業環境や用途に応じて選択しましょう。
例えば、建設現場などでは、黒球温度計を作業員の腰の位置に設置し、地面からの照り返しを考慮した正確なWBGT(暑さ指数)が測定できます。
また、AIを活用したWBGT予測システムも登場しています。気象データと過去のWBGT(暑さ指数)を学習し、数時間先のWBGT(暑さ指数)を予測できるシステムです。
このように、暑さは数値化して、熱中症の危険度を図ることができます。
熱中症対策として効果的な勤務体制の工夫は、企業の生産性維持と従業員の安全確保の両立に不可欠です。
交代制勤務の導入は、長時間の連続作業を避けるための有効な方法です。シフトを短縮し、複数の作業者で交代することで、暑熱への暴露時間を減らします。例えば、4勤2休の勤務シフトを採用し、作業負荷に応じてローテーションを実施するといった方法もあるでしょう。
また、短時間作業と長めの休憩を組み合わせる方法も効果的です。45分作業後に15分休憩を取るなど、作業時間を短くし適度な休憩を確保することで、熱ストレスの蓄積を防ぎます。
屋外作業については、日中の高温時間帯を避け、早朝や夕方に作業を集中させることが有効です。例えば、午前5-10時と午後4-8時の2シフト制を採用し、熱中症リスクの高い時間帯の作業を回避できるように作業時間を設定するといった工夫もあります。
さらに、定期的な水分補給タイムを設けることも重要です。1時間に1回、全員が水分補給を行う時間を設定し、脱水症状を予防しましょう。厚生労働省の「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」では、20〜30分ごとにカップ1〜2杯程度の水分摂取が望ましいとされています。
これらの対策に加え、WBGT(暑さ指数)に基づいた作業管理や、冷房完備の休憩所の設置など、総合的な対策を図りましょう。
従業員の健康管理は、熱中症予防において重要な柱です。厚生労働省の「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」や「職場における熱中症予防対策マニュアル」などに基づき、多くの企業が効果的な対策を講じています。
対策として、経口補水液の提供や塩分タブレットや塩バナナなどの熱中症対策食品を活用し、効率的な水分補給と栄養管理を取り入れましょう。
例えば、スマートフォンと連動して水分補給量を管理できるスマートボトルといった、IoT 機器を利用した熱中症予防システムを導入する方法もあります。
また、作業前には必ず健康チェックを行い、「のどの渇き」「めまい」「だるさ」などの症状を確認します。非接触型体温計で発熱を検知した場合は、作業を控えるよう指導することも重要です。
さらに、自己申告制度を整備し、体調がすぐれない場合は従業員が上司や管理者へ速やかに報告できる環境を整えることで、早期対応が可能になります。
近年は、ウェアラブル端末の活用も進んでいます。例えば、心拍数や体温をリアルタイムで測定し、異常があれば警告を出すシステムが導入されており、感覚に頼らない正確な健康管理が実現しています。このような技術は、特に過酷な現場で働く従業員の安全確保に大きく貢献しています。
これらの取り組みは、従業員一人ひとりの健康状態に応じた対策を可能にし、職場全体で熱中症リスクを低減させる効果的な手段といえるでしょう。
熱中症対策は業種によって異なるアプローチが必要です。製造業、建設・配送業、飲食業など、各業種特有の環境や作業内容に応じた対策が求められます。
ここでは、対策グッズや工夫を取り入れた効果的な熱中症対策のポイントを業種別に紹介します。
工場や製造業の現場は、作業環境の特性上、高温多湿になりやすく、熱中症リスクが高い環境です。そのため、効果的な熱中症対策が求められています。
まず、換気・空調・遮熱対策といった作業場の温度管理が重要です。例えば、スポットクーラーや大型扇風機、屋根用スプリンクラー、遮熱シート・遮熱塗料などを活用します。
ミストファンを設置し、気化熱による床面温度の低減や、作業エリア全体を28℃に保つ空調設備の導入などの取り組みが考えられるでしょう。
次に、作業スケジュールの見直しと休憩時間の確保も重要です。高温になる時間帯を避けるために早朝や夜間に作業を集中させるほか、45分作業後に15分の休憩を取るなど、適切なスケジュール管理が推奨されています。また、冷房完備の休憩所を設置し、体温を下げる環境を整えることも効果的です。
さらに、冷却グッズや冷却ウェアの活用も進んでいます。ファン付きウェアや保冷剤入りのベストは個人単位で冷却できるため、多くの現場で採用されています。特に空調設備が整わない場所では、作業者が快適に作業できる環境づくりが実現できるアイテムです。
このような対策によって、工場内での熱中症リスクを軽減し、安全で効率的な作業環境を整えましょう。
建設・配送業での熱中症対策は、作業環境の特性に応じた取り組みが重要です。
炎天下の作業時間短縮のため、これらの業界では様々な工夫が導入されています。建設現場では、WBGT(暑さ指数)が28を超える時間帯の作業を制限し、早朝や夕方の涼しい時間帯に作業を集中させること、交代制の導入によって暑熱への暴露時間を減らす取り組みがあります。
また、水分・塩分補給と服装の工夫も重要です。建設作業員には、こまめな水分補給を促すため、作業中でも飲みやすい携帯型の水筒が支給されています。塩分タブレットの常備も推奨されており、大量の発汗時にも役立つものです。
服装面では、ファンが内蔵されているヘルメットが広く普及しています。これは首元に風を送り、効果的に体温上昇を抑制するのが特徴です。また、吸汗速乾素材の作業着や冷却ベストの着用も推奨されており、体温調節をサポートしています。
さらに、早朝や夜間勤務の活用も進んでいます。特に宅配業界では、EV配送車の導入に伴い、車内の予冷システムが標準化され、集配作業の合間に短時間のクールダウンが可能になっています。
このように、熱中症リスクの軽減と作業効率の維持を両立させる取り組みが進められています。
厨房は火を常時使用することで高温多湿になりやすく、熱中症リスクが非常に高い環境です。
まず、キッチン内の換気とクーリングスペースの設置が重要です。調理で出た湯気や煙の中の油分が大量に付着している換気扇は、スムーズに排気されず、厨房内の温度が上昇します。定期的に換気扇やエアコンを掃除し、気化式冷風機やサーキュレーターを活用して、厨房内の換気と室内温度を均一に保つ工夫をしましょう。
厨房内には冷房完備の休憩スペースを設け、従業員が作業中に蓄積した熱を放散できる環境を整えます。保冷剤や冷水ボトルを備えれば、短時間でも体温を下げることが可能です。
また、水分補給や休憩ルールとして、スタッフ同士で声を掛け合い、1時間ごとの水分補給を行うこともおすすめです。塩分やミネラル補給にはスポーツドリンクや塩タブレット、調理で使う梅干しや塩分が強い食品も良いでしょう。休憩中にはユニフォームを脱いで体にこもった熱を逃す習慣づけも大切です。
さらに、ユニフォームの素材選びと冷却アイテムの活用も大切です。水で濡らしたタオルを首周りに巻いたり、通気性のよい生地で作られたコックコートを導入したりといった方法があります。
熱中症予防として、企業や地方団体が効果を挙げた成功事例を紹介します。
従業員の安全と健康を守るために、実際に効果を発揮している企業の取り組みをぜひ参考にしてください。
熱中症対策は、業種や作業環境に合わせた取り組みを実施することが重要です。特に、高温環境下での作業が多い業種は、熱中症リスクが高いため、効果的な対策が不可欠です。
例えば、建設業は現場や地域、作業員の状況に応じた柔軟な対策が実施されています。主な取り組み事例として、日陰やエアコン付き休憩所の設置、遮光ネットによる日よけ、30分または1時間ごとの水分・塩分摂取、ファン付き作業服の推奨などです。
また、作業員同士の相互確認や定期的な巡視による体調チェックも導入している企業が多い対策です。さらに、熱中症に関する注意事項の掲示や水分補給のチェック表記入など、意識向上のための取り組みもあります。
その他にも、エアコンの設置が難しい作業場所であれば、スポットクーラーや業務用扇風機の設置なども効果的です。さらに、救急救命講習受講者の配置や熱中症キットの常備など、緊急時対応も含めた総合的な対策を取り入れている事例が多くあります。
個々の体調管理として、睡眠不足や過度の飲酒、朝食抜き、発熱の有無などをチェックすること、持病に合わせた健康管理を行うことも有効です。
これらの総合的な対策により、熱中症による重大事故の発生を未然に防ぐことが求められます。
地方公共団体が熱中症対策に取り組む意義は、地域住民の命と健康を守るだけでなく、地域全体の安全性と持続可能性を向上させる点にあります。気候変動の影響で高温化が進む中、熱中症リスクが増大しており、特に高齢者や子どもなどのリスクが高い住民への配慮が求められています。
例えば、東京都豊島区では、民生委員による熱中症予防の啓発運動に取り組んでいます。気温が急上昇する前の6月頃から8月の間に実施されている、地域見守り活動の一環です。地域に暮らす75歳以上の高齢者を対象に、自宅に訪問し、熱中症対策を啓発するチラシや冷却グッズの配布を行なっています。
また、地方公共団体では、熱中症対策を担当する部局が複数あることが特徴です。そこで、統一的な対策ができるよう、他部局と連携することが重要になります。
例えば、岐阜県多治見市は、2022年に最高気温40.0℃を記録した地域です。関係部局と多治見まちづくり株式会社が連携し、熱中症対策部会を立ち上げています。これにより、円滑な情報共有と検討会の実施、事業計画の策定などを適切なタイミングで実施できるようになりました。他にも、フリーペーパーによる情報発信も提供しており、普及啓発も行なっています。
このように、地方公共団体は、地域特性に応じた柔軟な対策を講じることが重要です。
企業が熱中症対策を実施することは、従業員の健康と安全を守るだけでなく、業務効率の向上やリスク管理にもつながります。
熱中症の症状や応急処置、予防策について、またWBGT(暑さ指数)を活用した環境管理や休憩ルールの重要性について理解を深めましょう。
また、成功事例を通じて、企業がどのように対策を導入し効果を上げているかを紹介しました。これらの情報をもとに、自社に適した対策を実践し、安全で快適な職場環境を整えましょう。
私たち日本シグマックスは、作業中に身体を冷却できる冷却服「メディエイド アイシングギア ベスト」で、酷暑環境で働く人の安全を守ります。
「メディエイド アイシングギア ベスト」は、ペルチェにより冷却された水がベストに内蔵されたパッド内を循環し、人体を快適な温度に保つ水冷式の冷却服です。
当社独自の特許取得済のアイシング技術(※)で、タンクレスながらも広範囲かつ効率的に人体を冷却し、着用した人が快適と感じる温度管理と、作業性・可動性の両立を実現しています。
医療機器やサポーター製品で培った技術を詰め込んだ、日本シグマックスこだわりの製品です。(※熱交換装置およびウェア 第7576853号)
「メディエイド アイシングギア ベスト」で暑さを克服し、快適な作業環境を実現しませんか?詳細や購入については、公式サイトでお問い合わせください。

準備はバッテリーの充電のみ。酷暑でも5時間冷感が持続するペルチェ×水冷式の「速・軽・快」な冷却服。
詳しくはこちら
シグマックス・MEDIAID事務局
シグマックス社員が仕事の中で得た知識から、知っておくと嬉しい・役立つ情報を、生活者の視点から発信しています。
MEDIAID(メディエイド)は整形外科で
確かな実績を持つ
日本シグマックスの
サポーター専業ブランドです。
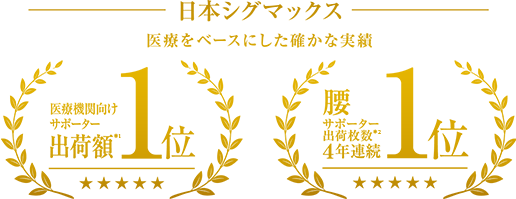 ※MEDIAIDは日本シグマックスのブランドです。
※MEDIAIDは日本シグマックスのブランドです。
※1:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2023年度メーカー出荷額ベース
※2:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2020~2023年度メーカー出荷枚数ベース