2025.04.22 最終更新日: 2025.04.28

日本の工場における暑さ対策は、企業にとって喫緊の課題となっています。気候変動の影響で夏季の気温が年々上昇する中、工場内の高温環境は労働者の健康と生産性に深刻な影響を及ぼしています。
本記事では、工場の暑さ対策の必要性や具体的な実践方法、効果的な取り組み事例を紹介します。さらに、暑さ対策に活用できる補助金制度についても解説していますので、企業が取り組むべき対策の全体像を確認できるでしょう。
工場の暑さ対策が必要な理由として、労働者の健康リスクの増大や生産性の低下、法的義務などが挙げられるでしょう。
ここでは、工場内の高温環境が人や製品にもたらす影響、法的義務、暑さ対策のメリットを詳しく解説します。
工場内の高温環境は、労働者の健康、生産性、そして製品の品質にも多大な影響を及ぼします。
まず、労働者の健康リスクについて考えてみましょう。高温環境下での作業は、熱中症や脱水症状のリスクを著しく高めます。
具体的に、総務省「熱中症による救急搬送状況(平成20年~令和5年)救急搬送人員及び死亡者数(年別推移)」によると、2023年の仕事場(工場を含む)での熱中症搬送数は9,324人で、過去5年間で最多となったという報告があります。
特に、重度の熱中症は生命に関わる危険性があり、企業にとっても大きな損失です。
次に、生産性の低下も深刻な問題です。高温環境下では、労働者の集中力や判断力が低下し、作業効率が悪化します。特に、26℃を超える環境では認知機能が低下し始め、35℃以上では正確さと意思決定能力が著しく損なわれるとされているのです。
さらに、製品の品質への影響も見逃せません。多くの工業製品は、適切な温度管理下で製造する必要があります。何よりそれを管理したり製造工程に関わる作業者の集中力や判断力が低下することは、製品の精度に影響を与えるリスクがあるでしょう。
これらの影響は、夏季だけの一時的な問題ではありません。気候変動の影響で、高温環境下での作業が必要となる期間は年々長期化しており、企業にとって長期的な対策が不可欠となっているのです。
工場の暑さ対策は、企業の自主的な取り組みではなく、労働安全衛生法に基づく企業の責任です。
労働安全衛生法では、事業者に対して労働者の安全と健康を確保するための措置を講じることを義務付けています。
具体的には、第22条で「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」と定められており、その中には「高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害」が含まれています。
2025年の労働安全衛生規則の改正により、事業者は「WBGT(暑さ指数)を把握し、基準値を超えないよう必要な措置を講じること」が義務付けられました。この改正は、近年の気候変動による猛暑を背景に、より具体的な暑さ対策を企業に求めるものです。
また、厚生労働省が定める「職場における熱中症予防対策ガイドライン」も、企業が遵守すべき重要な指針であり、WBGT(暑さ指数)に基づいた作業環境管理、作業管理、健康管理の3つの観点から具体的な対策が示されています。
例えば、WBGT(暑さ指数)が基準値を超える場合は、作業時間の短縮や休憩時間の延長、水分・塩分の摂取促進などの措置を講じることが求められています。
これらの法的義務や安全基準の遵守は、単なるコンプライアンスの問題ではありません。適切な暑さ対策を講じることで、労働者の安全を確保し、生産性を維持するとともに、企業の社会的責任を果たすことにもつながります。
工場における適切な暑さ対策は、労働者の健康リスク回避のためだけではなく、多くのメリットをもたらします。
まず、労働者のモチベーション向上が挙げられます。快適な職場環境は、従業員の満足度を高め、長期的な定着率の向上にもつながるでしょう。特に、温度や湿度などの空調管理は、働きやすさに大きく影響を与える要因です。
また、生産性と品質の向上も重要なメリットです。適切な暑さ対策は、作業効率を改善し、製品品質の安定化にも寄与します。直接的な経済効果をもたらすだけでなく、結果として、良い製品をお客様に届けられるため、顧客満足度の向上にもつながる重要な成果となるでしょう。
さらに、企業イメージの向上も見逃せないメリットです。労働環境改善への積極的な取り組みは、社会的評価を高め、優秀な人材の獲得にも有利に働きます。労働環境が整っており、働く人の健康を守る取り組みをしている企業は、企業イメージが高まるでしょう。
加えて、適切な暑さ対策は、長期的なコスト削減にもつながります。熱中症による労働災害や生産性低下のリスクを軽減することで、潜在的な損失を防ぐことが可能です。
このように、工場の暑さ対策は、労働者の健康と安全を守るだけでなく、企業の競争力強化と持続可能な成長にも直結する重要な経営戦略の一つといえるでしょう。
工場はその特有の構造によって、季節を問わず暑くなりやすい環境です。企業は、暑さ対策として、WBGT(暑さ指数)測定による温度管理や工場の設備を改善することが基本となります。
ここでは、工場の暑さ対策の基本から実践方法まで詳しく紹介します。
工場内が特に暑くなる理由は、立地や構造、使用されている設備などの問題が大きく影響しています。
まず、工場の構造自体が熱を蓄積しやすい特徴を持っています。多くの工場は、広い空間を確保するために高い天井と大きな床面積を持つ設計です。天井が高い工場は、空調効率も悪くなり、熱が上昇して天井付近に滞留しやすく、効率的に排熱されません。
工場で使用される機械や設備も大きな熱源となります。例えば、金属加工機や溶接機、大型プレス機などは稼働時に大量の輻射熱が発生し、工場内が高温になりやすいのです。
さらに、工場の屋根や壁の材質も重要な要因です。多くの工場で使用される金属製の屋根や壁は熱伝導率が高いため、外部からの熱を内部に伝えやすい特性があります。特に、断熱処理が不十分な場合、夏季の直射日光による屋根の温度上昇が室内環境に直接影響を与えるでしょう。
これらの要因が相互に作用することで、工場内の温度は外気温よりも大幅に高くなる可能性があります。
したがって、効果的な暑さ対策を講じるためには、これらの要因を総合的に考慮し、建物構造、設備配置、換気システム、断熱性能などを見直す必要があるのです。
「【企業向け】夏以外にも起きる熱中症とは?!事前に予防法がわかる熱中症対策ガイド」の記事へ
工場内の温度管理の基礎となるのが、WBGT(暑さ指数)の測定です。WBGT(暑さ指数)は、温度、湿度、輻射熱を取り入れた総合的な指標で、熱中症のリスク評価に広く用いられています。
WBGT(暑さ指数)の測定には、専用の測定器を使用します。WBGT測定器は、温度、湿度、黒球温度を同時に測定し、自動的にWBGT(暑さ指数)を算出できる機器です。測定は、作業者の行動範囲内で、地上から1.1〜1.5m程度の高さで行います。特に、屋内なら熱源の近くや、屋外なら直射日光の当たる場所など、高温になりやすい箇所での測定が必要です。
測定頻度については、1日のうち最も暑い時間帯に1回以上の測定が推奨されています。ただし、天候や作業内容の変化に応じて、適宜追加の測定を行うことが望ましいでしょう。
測定したWBGT(暑さ指数)は、厚生労働省の熱中症ガイドラインに基づいて評価します。例えば、軽作業の場合、WBGT(暑さ指数)が28を超えると、作業時間の短縮や休憩時間の延長などの対策が必要となります。作業内容によって注意すべきWBGT(暑さ指数)が変動するため、業種・作業環境に合わせた評価を行うことが大切です。
さらに、環境モニタリングシステムも注目されています。工場内の複数箇所にセンサーを設置し、リアルタイムでWBGT(暑さ指数)をモニタリングできるシステムです。クラウド上でデータを管理することで、管理者はスマートフォンやタブレットからいつでも工場内の環境を確認できます。
工場の暑さ対策として設備投資をするにあたっては、一時的な問題解決だけでなく、中長期的な視点が必要です。従業員の健康と安全を守り、生産性と製品の品質を保つためにも必要な対策といえます。
例えば、以下のような設備投資が挙げられるでしょう。
● 工場の外装などの改善(遮熱シート・断熱材・屋根や壁の塗装)
● 換気の最適化(排熱対策・ファンの設置)
● 空調設備の見直し(スポットクーラー・大型扇風機の活用)
遮熱シートや断熱材の施工、遮熱塗料による屋根や外壁の塗装は、外部からの熱侵入を大幅に抑制します。これにより室内温度の上昇を防ぎ、空調負荷を軽減できるでしょう。長期的には電力コストの削減にもつながり、作業環境の改善と省エネを同時に実現できます。
また、適切な換気システムの導入は、工場内の熱気滞留を防ぎ、作業環境を改善します。大型換気扇や天井ファンを設置すると、効率的な空気循環を実現できるでしょう。特に熱源となる機械設備周辺の局所排気は効果的です。
さらに、空調設備の見直しも、工場内の暑さ対策において必要です。スポットクーラーや大型扇風機の適切な配置は、局所的な温度管理を可能にします。特に高温作業エリアや熱源近くでの活用が効果的です。
これらの設備投資には一定の費用がかかりますが、多くの場合は長期的なコスト削減や生産性向上によって回収できます。さらに、政府や地方自治体で提供する補助金制度を活用することで初期投資の負担を軽減できる可能性があるため、自社が所在する地域の自治体に問い合わせ、利用可能な制度を確認することをおすすめします。
工場の暑さ対策は、従業員の健康と安全を守り、生産性と製品の品質を維持するために不可欠です。熱中症リスクの軽減、作業効率の向上、労働環境の改善による従業員満足度の向上、そして事故防止にもつながります。
ビルの保守管理をしている企業では、保守・修理・工事を行うエンジニアの熱中症対策として、空調管理ができる作業服を全社導入した事例があります。
以下、引用しているため参考にしてください。
「ビルを、まるごと、心地よくする。」三菱電機ビルテクノサービス株式会社(社長:吉川正巳)では、エレベーターの昇降路・機械室内や空調設備のある屋上等、保守・修理・工事などを行うエンジニアの熱中症対策として、空調作業服(※空調服)を2018年6月から全社導入します。
当社エンジニアが作業を行う場所は、夏場は気温が高くなりやすく、熱中症などの発生が危惧されます。その解決策として、2017年度、一部支社において空調服の試験導入を行い、労働環境の改善が確認されました。実際に着用したエンジニア(794名)にアンケートを実施したところ、空調服の着用で、95.3%が「効果がある」と回答。次いで、「熱中症予防に効果がある」(81.5%)、「肉体疲労の軽減に効果がある」(53.0%)の結果となりました。この結果により、今夏から働き方改革の一環として、当社および協力会社 の約5,500名(約11,000着:1人あたり1~2着)に配布します。
引用元:三菱電機ビルソリューションズ株式会社|ニュースリリース・お知らせ
空調作業服を全社導入|2018年06月14日掲載
https://www.meltec.co.jp/press/180614.html
この事例は、適切な暑さ対策が労働環境の改善と従業員の健康維持に大きく寄与することを示しています。空調作業服の導入により、熱中症リスクの低減と作業効率の向上が実現できたとのことです。
このように、企業が積極的に新技術を取り入れ、従業員の安全と快適性を重視する姿勢は、働き方改革の好例といえるでしょう。
工場の生産効率は、室温と密接に関わっています。快適な室温を保つことでタイプミスが減少し、タイピング量が増加したという研究結果も報告されています。
工場全体の空調効率を高めるためには、スポットクーラーの設置、ビニールカーテンによる空間遮断、断熱フィルムや断熱塗装の活用が有効です。また、熱の発生源には吸排気フードを設置し、自動空調システムを導入することで、より効率的な温度管理が可能になります。
作業員一人ひとりの対策としては、保冷材付きベストや空調管理ができる作業服、速乾吸収性の高いインナー、冷却タオルなどがおすすめです。これらのアイテムを組み合わせることで、体感温度を下げ、快適な作業環境が維持できます。
さらなる熱中症対策として、熱中症の症状をスタッフと共有することや、水分・塩分の自由補給、休憩室の設置も重要になるでしょう。
工場の暑さ対策は、従業員の快適性向上だけでなく、生産効率の改善にも直結します。スポットクーラーや断熱材の活用、個人用冷却アイテムの導入など、自社に合わせた対策を導入しましょう。
工場の暑さ対策は、工場の設備投資や作業員一人ひとりの対策のほかにも、様々な補助金制度を活用することで、初期投資の負担を軽減できます。
ここでは、工場の暑さ対策に活用できる補助金、省エネルギー対策と暑熱対策を同時に行う方法を確認してみましょう。
工場の暑さ対策を実施する際、様々な補助金制度を活用することで、初期投資の負担を軽減できます。
主な補助金制度は、以下の3つです。
● サプライチェーン対策補助金
● エイジフレンドリー補助金
● 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業
「サプライチェーン対策補助金」は、経済産業省が提供する補助金であり、国内産業におけるサプライチェーンの強化を目的とした、建物・設備・システムの導入などに対する補助金です。工場等の施設の建設費や設備機器装置費が補助されることから、募集要件によっては熱中症対策に関連する工事も適用される可能性があります。
| 補助対象者 | 大企業、中小企業等 ※補助対象事業には条件があります。 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 建物・設備・システムの導入 |
| 補助上限 | 100億円(1次公募時は150億円) (中小企業特例事業は5億円) |
| 補助率 | 原則 大企業1/2以内、中小企業2/3以内 |
参照元:経済産業省「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」より
なお、こちらの助成金は、自治体の予算によって受付している年と受付していない年があります。そのため、ご利用時には対象の自治体にお問い合わせください。
「エイジフレンドリー補助金」は、厚生労働省による補助金制度であり、中小企業による高齢労働者のための設備導入や健康促進を目的としています。高年齢労働者がいる工場で、暑さにより労働者が倒れる労働災害防止のための対策としても適用可能です。
| 対象事業者 | 中小企業事業者であって ・高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している ・対象の高年齢労働者が補助対象に係る業務に就いている |
|---|---|
| 補助対象 | 1年以上事業を実施している事業場において、高年齢労働者の身体機能の低下を補う設備・装置の導入その他の労働災害防止対策に要する経費(機器の購入・工事の施工等) |
| 補助上限 | 100万円 |
| 補助率 | 1/2 |
参照元:厚生労働省「エイジフレンドリー補助金について」より
「工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業」は、環境省による補助金制度であり、CO2削減に寄与する設備投資を対象としています。暑さ対策と省エネを両立する設備導入においても適用可能です。
| 補助事業の内容 | ① CO2削減計画策定支援 ② 省CO2型設備更新支援 ③ 企業間連携先進モデル支援 |
|---|---|
| 補助上限・補助率 | ① 補助率3/4、補助上限:100万円 ② 標準事業:補助率1/3、補助上限:1億円 大規模電化・燃料転換事業:補助率1/3、補助上限:5億円 中小企業事業:補助上限0.5億円 ③ 補助率1/3、1/2、補助上限5億円 |
| 補助率 | 1/2 |
参照元:環境省「令和6年度 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)の公募開始について」より
その他に、「団体経由産業保健活動推進助成金(労働者健康安全機構)」があります。詳細については、対象機関にお問い合わせください
工場の暑さ対策と省エネルギー対策を同時に実施することは、作業環境の改善と長期的なコスト削減にもつながります。
効果的なのは、屋根や外壁に遮熱シートを取り付ける方法です。輻射熱は断熱材で遮断することが難しいため、受け止めたり吸収したりするのではなく、跳ね返すことが大切です。
アルミ製の遮熱シートは、この輻射熱を約97%反射し、建物内への熱放射を大幅に減少させることができます。これにより体感温度が下がり、空調コスト削減や省エネが期待できるでしょう。
窓ガラスにも遮熱フィルムを貼ることで日射熱の侵入を抑えられます。これらの設備改修は比較的低コストで実施できるため、多くの工場で導入されている対策です。
これらの対策を取り入れ、作業環境全体の改善と長期的なコスト削減を目指しましょう。
工場の暑さ対策は、従業員の健康と安全を守り、生産性を向上させ、さらには企業の社会的責任を果たすための重要な取り組みです。自社の状況に応じた最適な対策を講じることで、より快適で効率的な労働環境の実現が期待できます。
具体的な対策としては、工場構造の改善や換気システムの最適化、空調設備の見直しなどが挙げられます。さらに、遮熱シートの設置により、省エネルギー対策も同時に実現可能です。
これらは初期投資が必要になりますが、長期的な生産性向上やコスト削減につながる対策です。補助金制度の活用も視野に入れて、経済的な負担を軽減しながら導入しましょう。
私たち日本シグマックスは、作業中に身体を冷却できる冷却服「メディエイド アイシングギア ベスト」で、酷暑環境で働く人の安全を守ります。
「メディエイド アイシングギア ベスト」は、ペルチェにより冷却された水がベストに内蔵されたパッド内を循環し、人体を快適な温度に保つ水冷式の冷却服です。
当社独自の特許取得済のアイシング技術(※)で、タンクレスながらも広範囲かつ効率的に人体を冷却し、着用した人が快適と感じる温度管理と、作業性・可動性の両立を実現しています。
医療機器やサポーター製品で培った技術を詰め込んだ、日本シグマックスこだわりの製品です。(※熱交換装置およびウェア 第7576853号)
「メディエイド アイシングギア ベスト」で暑さを克服し、快適な作業環境を実現しませんか?詳細や購入については、公式サイトでお問い合わせください。

準備はバッテリーの充電のみ。酷暑でも5時間冷感が持続するペルチェ×水冷式の「速・軽・快」な冷却服。
詳しくはこちら
シグマックス・MEDIAID事務局
シグマックス社員が仕事の中で得た知識から、知っておくと嬉しい・役立つ情報を、生活者の視点から発信しています。
MEDIAID(メディエイド)は整形外科で
確かな実績を持つ
日本シグマックスの
サポーター専業ブランドです。
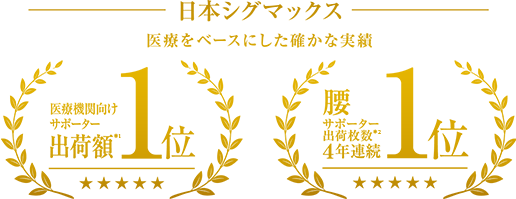 ※MEDIAIDは日本シグマックスのブランドです。
※MEDIAIDは日本シグマックスのブランドです。
※1:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2023年度メーカー出荷額ベース
※2:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2020~2023年度メーカー出荷枚数ベース